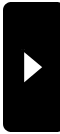2025年03月25日
我が家は今年も午前中はLAD観戦

米大リーグが3月末から開幕する。一足早く3月18、19日にドジャースとカブスの開幕戦が東京ドームで行われた。二刀流復活や3年連続MVPとサイ・ヤング賞の同時受賞なるかなど、今年も大谷翔平選手の活躍に期待が膨らむ。
妻はプロ野球をはじめ野球にとんと興味がなかった。子どもの頃、父親らが点けたラジオやテレビで野球放送が始まると、すぐその部屋から出ていったという。そんな彼女が昨年梅雨明けごろだったか、「今日、大谷君の試合はあるの」と急に言い出し、それから午前中のリビングは「お茶の間スタンド席」に変わった。
妻は野球の試合ルールをほとんど知らない。観戦しながら私が横から「副音声解説」している。テレビのニュースやスポーツ番組では、大谷選手のホームランシーンばかり流すので、彼女は毎試合ホームランを打っていると思っていた。実際の試合を観戦すると、連続三振やヒットが出ないままゲームセットを迎えることもある。そんな日は、午前中を全く無駄に過ごしたかのような顔つきになった。
それでも大谷選手がプレーする試合を毎回楽しんでいるのは、野球が大好きな「純粋野球少年」の姿勢に魅了されたからだろう。「大谷の推しだが野球知らぬ妻」。毎日新聞掲載の「仲畑流万能川柳」の句だ。
ドナルド・トランプが1月末から再び米国大統領に就任した。アメリカファーストの姿勢を一層鮮明にしている。「米国人アスリートの職場を奪う」からと、大リーグなどから日本人をはじめ外国人選手を排斥しろと、言い出したりしないか心配になる。
2025年02月22日
「コメを食うとバカになる」論が引き金

小学校の低学年の頃だったか、大人たちが世間話の中で「コメを食べるとバカになるっちよ。うちの子に何ば食べさせたらよかかね」と話しているのを何度か聞いた。大人たちの、単なるうわさ話と思っていた。
慶應義塾大学の医学部教授が1958年に「頭脳―才能をひきだす処方箋」という本の中で「日本が欧米に劣っているのは米を食べているから」と提唱していた。小麦食品業界はこの本をベースに「米を食べると馬鹿(ばか)になる」というパンフレットを作成し、数十万枚も配布したそうだ。当時の大人たちは、このことを真に受けていたのだ。
30代の頃、職場と自宅の中間地点が繁華街の天文館。足蹴(あしげ)く通った飲み屋で、コメの研究者の鹿児島大学農学部・U教授と知り合った。「コメの旨(うま)さの決め手は開花期間の長さ。だから、花が咲く時期に涼しくなる伊佐地方のコメは南国でも美味(おい)しい」などコメ談義をしてくれた。しかし「文部省はね、論文のタイトルに『米』の一文字でも入ると、研究費を払わなくなった。学問の世界にも減反政策。将来、主食はどうなるんだ」と、現在の騒動を予言するかのように憂いていた。
医学部教授のトンデモ本の影響もあり、62年をピークにコメの消費量が減り、70年に減反政策が始まった。2018年減反政策は終わったが、引き続きコメから転作する農家への補助金は継続しており、減反は続いている。令和の米騒動を政府は流通問題で片付けようとしている。市場に出せるコメの生産量を的確に把握し、政策転換をしなければ、日本人の胃袋は主食を含め海外に握られてしまうのではないか。
2025年01月25日
みさなん このことばが わりかますか

こんちにはみさなんおんげきですか。わしたはげんきです。
この文を間違って読んだ人はおかしいと思わず、間違わずに読んだ人はアレっと思っただろう。あなたも「こんにちは皆さんお元気ですか。私は元気です」と読みませんでしたか。
このように、文章に含まれる単語を構成する文字を並べ替えても、多くの人がその文章を問題なく読めてしまうことをタイポグリセミア現象と呼ぶそうだ。この現象が起きるのは「単語の最初と最後の文字は正しいもの」の場合などに限られる。日本語では「単語を構成する文字は6文字前後以内」などの条件が必要という。
毎日新聞の3面下段に読者投稿の「仲畑流万能川柳」という名物コーナーがある。コピーライターの仲畑貴志さんが選句している。万能とついているのは、川柳はもちろん、俳句や一行詩、コピー調など何でもありのニューウェーブ川柳欄ということで命名された。
「みなんさは ごぞんじすでか 読める(タイポグリ)誤字(セミア)(東京・ホヤ栄一)」の句がこの欄に載り、読み間違えたことでタイポグリセミア現象を引き起こす文章のことを知った。
この現象を逆手にとった広告もある。老舗和菓子店が名物のどら焼きを改良した。「ぜたっい に ばれない ように どやらき の リニュアールを おなこいました」のコピー文で、どこをリニューアルしたか購買者にクイズを出した。
タイポグリセミア現象の読み間違いは、笑い話で済ませられる。ネットでの詐欺や政治・選挙でのフェイクな言葉の「読み間違い」は、絶対に避けなければ。
2024年12月27日
奄美とメキシコによく似た舞がある

メキシコに住む二女が、地域の祭典をSNSにアップした。「サンマルコス祭」といって3週間開かれる大規模なもの。メキシコ最大級の祭とも言われ、地元や同国の人々だけでなく、外国からも観光客が遊びにくる。人口90万人ほどの穏やかな街に、期間中の来場者は800万人を超える。
祭りの期間、パレード、音楽コンサート、ダンス、芸術展、バルーンフェスティバル、サーカス、闘牛、打ち上げ花火などのアトラクションから、家畜の展覧会、地元の食品や工芸品の展示などのイベントで賑わう。日本パビリオンも設置され、和太鼓などの伝統音楽の演奏も披露されており、「小さな万博」のような賑わいぶりという。
娘が映した動画は、無料のお祭り広場の舞台の模様だ。ソンブレロを被った男性らが、ギターとバイオリンを奏でるマリアッチ。カラフルな衣装で男女が躍るハラベ・タパティオ。そんな中、素朴な面を付けた踊りがあった。円錐型の帽子の縁にはカラフルな色の飾り、衣装は薄い生地の白いシャツとズボン。棒か杖のようなものを手に、ステップを踏む仕草があった。
その姿や所作が、県の民俗芸能祭りで見た奄美の加計呂麻島の「諸鈍シバヤ」を演じる男衆にそっくりなのに驚いた。違いは男衆の絹の上着の色が黒いことくらいだ。
遠く離れた地域によく似た文化が見られるのには「なんらかの条件さえ満たされれば、必然的に生まれる」という普遍人類学的考えがある。しかし、太平洋を挟んだ両地域での酷似した舞いは、遠い昔に漂流でたどり着いた人によって伝えられもの、との途方もない考えに私は軍配を上げる。
2024年11月21日
焼き物の色復元と「青い謎」の解明も

鹿児島市本庁舎は、都道府県庁所在地の中では、静岡・名古屋・京都と並んで数少ない戦前の建築物だ。1937年に完成し、戦火もくぐり抜け98年に国の登録有形文化財になっている。
庁舎正面のアーチ状の玄関に、直径約80㌢のレリーフが正面に4枚、側面に2枚ずつある。唐草模様が中央の杯を囲むデザインだ。設置から85年以上が経ち、ひび割れや一部パーツが欠けていることから、このほど本格修復されると報道された。レリーフは薩摩焼の名陶工、初代長太郎(1871~1940年)の作。当時の岩元禧(き)市長と親交があり依頼された。うわぐすりに「辰砂釉(しんしゃゆう)」が使われ、完成時は緑がかった色だった。今は青く着色されている。
40年ほど前、知人から「長太郎さんのレリーフが市役所の玄関にある」と聞き見にいった。長太郎とは思えない色に疑問を持ち調べた。鹿児島市史第3巻(81年発行)の「年表」に「(44年)市庁舎、黒の迷彩色に塗り替える」「(53年)10月戦時中黒の迷彩色に塗りかえた市庁舎の垢(あか)落しはじまる」の記述を見つけた。
修復の助言役は、初代の孫で4代目の有山長佑さん(88)。彼が記者に「大学進学などで故郷を離れていた間に釉薬(ゆうやく)が作り出す緑がかった色味が、(ペンキで塗られて)青色に変わっていて驚いた」と話している。
市誌と長佑さんの記憶を重ねると、53年の「垢落し」の時に青く塗られたと推察される。修復で初代の色がよみがえり、「青色変化」の謎も解明されればと期待したい。
市庁舎の迷彩色が、空襲を免れた原因かは定かではない。再びビルを黒く塗るような時代にしてはならない。
2024年11月03日
最低賃金は全国一律が世界の常識

今年も10月から、最低賃金が引き上げ改定された。適用されるのは、事業規模にかかわらずすべての民間企業。この金額未満で働かせると、使用者は罰則の対象になる。直接的な影響を受けるのは、パートやアルバイトなどの非正規労働者だ。
一方、公務職場の非正規職員の賃金もこの額が考慮されている。そのため、最低賃金が上がれば、民間、公務の正規職員の賃金にも波及がある。その結果、退職者の年金額も調整される場合がある。
最低賃金の引き上げは、多くの国民の所得、暮らしに影響を与える。しかし今の地域別の金額のままでいいのか疑問だ。
改正額を見ると、東京都1163円(前年比+51円)、鹿児島県953円(同+56円)で、その差は210円。格差が一番大きかった2014年に比べると縮まっている。しかし月160時間働くと月約3万4千円、年で40万円ほどの差になる。全国で一般的に流通する食料品や衣料品などの価格を見ても、生活にかかる最低限の金に、都市部と地方でそこまで違いがあるとは思えない。
最近、人口ピラミッドを調べる必要があった。20年の年齢別人口構成の全国の形に比べ、九州や東北各県は20~34歳の層が少なく、逆に東京は極端に多い。最低賃金の低い地域から、高い地域に移動していることが一目で分かった。
世界的に見ても、地域別最低賃金はわずか3%で、全国一律が大多数だ。自民党総裁選で候補者の多くが「改革」を訴えていた。「全国一律の最低賃金」こそ大胆な地方改革と思うが。世襲議員候補らは「民の竈(かまど)」など気にならないようだ。
2024年08月31日
新紙幣発行による経済効果に疑問

20年ぶりとなる新紙幣3種類が発行された。電子マネーやカード支払いが多く、紙幣利用が減っているので関心は薄かった。数週間して手にしても、以前の新札発行時の様な高揚感はなかった。
初めて自分の物を買った紙幣は、駄菓子屋で支払った1円札だ。小学校に上がってまもないころと思うが、当時はまだ50銭の値がついたものがいくつか置いてあった。煎餅、あめ玉、ガラス瓶に入れられた駄菓子、ビー玉(住んでいた北九州では「だんちん」と呼んでいた)、相撲取りや野球選手のカードなど。
買い物の駄賃として母からよれよれの1円札をたまにもらうと、紙幣を握りしめ一目散に駄菓子屋に。1円で二つの物が買えることがうれしかった。でも店に入ると、お菓子か遊び道具かそれともといつも目移りし迷っていた。
新紙幣の発行で、1・6兆円の経済効果が期待できると報道されている。新紙幣に対応するため、自動販売機や券売機、セルフレジ、ATMなどの機種変更によるもの。しかし機器が新しくなっても、バスや電車の乗客やラーメン屋の客が増えるわけではない。ある意味無駄な費用負担だ。風が吹くと桶屋が儲かる式の波及効果はほとんどない。自販機メーカーや関係企業が儲かるだけである。
これを経済効果と呼ぶには、経済人・渋沢栄一も違和感を覚えるのでは。これから防衛増税の議論が本格化していく。増税されれば、その分は兵器産業が儲けることになる。そこで政府は、国民に納得感を持ってもらうため「防衛増税は数兆円の経済効果をもたらすので、増税にご理解を」などと説明をするだろうか。
2024年07月25日
商業主義に「負けた」アマチュアリズム

パリオリンピックは7月26日に開会式を迎える。私にとっての五輪といえば、1964年10月の東京大会が一番印象に残っている。大会期間中、授業が午後から休講になり、毎日テレビ観戦したことも一つの要因だが。
この年は中学2年生だった。日本初開催とあって、新学期が始まると五輪関連が授業でよく取り上げられた。近代五輪の父と呼ばれるクーベルタン男爵の名前は、何度も聞かされた。彼の「オリンピックは、勝つことではなく参加することに意義がある」の言葉が書かれた紙が、教室の後ろの壁に貼られていた。やんちゃ盛りの生徒は、試験のたびに「テストはいい点を取ることではなく、参加することに意義がある」と、ふざけあった。
今ではオリンピック憲章からも消えてしまったが、営利を目的としない「アマチュアリズム」こそが、オリンピックの理念なんだと先生らは強調していた。生徒らの理解は「プロ野球があるから正式なオリンピック競技に野球がないんや」「力道山が生きててもレスリングには参加できんのか」のレベルだったが。
アマチュアリズムを掲げた五輪も、今では大会がビジネスショー化し、スポーツ組織や企業が、収益を最大化するための絶好のビジネスチャンスになった。関係者の汚職まで生みだしている。
今春、テレビドラマの「不適切にもほどがある」が話題になった。宮藤官九郎の脚本で、昭和と令和のコンプライアンスやジェンダー問題のギャップに一石を投じるような物語だった。クーベルタンは草葉の陰で、五輪の商業主義への変節に「ふてほど」と眉をひそめていることだろう。
2024年06月26日
「蛍の名所」に取り組むスポーツ公園

雨が早朝から降っていたが、夕暮れ時には上がった。こんな日はよく飛んでいると思い、近所の丘の上にあるスポーツ公園に蛍狩りにでかけた。
敷地の奥には、整備される前の森林、草むらが残されている。そこを流れる小川から池のあたりまでの200メートル区間をゆっくり歩く。薄暗いなかで、葉に止まったり水辺の上を飛ぶ蛍火が見え始めた。ゾーンごとに十数匹ずつ光を点滅させながら乱舞していた。
この蛍は、施設の管理者がゲンジボタルの幼虫と、餌になるカワニナを6年前から放流し育てている。一昨年は三十数匹、それが倍倍と増え今年は131匹までカウントできた。ここ数年、大学の先生を講師に「観察会」も開かれている。今年は蛍の数の7倍を超える950人が参加した。
私が訪れた日は、10人ほどが鑑賞していた。飛んでいる蛍にそっと手を差し出すと、私の指先に止まってきた蛍がいた。薬指の先で淡い黄緑色を発光している。なかなか手から離れない。大きく腕を振ると、すーっと渓流の方に飛び去って行った。つかの間メルヘンな気分を味わった。
「蛍の名所」にしたいというこの公園のふもとは、近郊農業の田んぼが広がる地域だった。以前住んでいた人は「40年前は5月になると家の前の川をたくさんの蛍が飛んでいたよ」と。その後、宅地開発などで徐々に姿を消したそうだ。
雀の涙ほどの減税に「恩恵」を感じろと、給与明細に減税額の明記を義務付けた総理。初夏の風物詩を堪能できた「恩恵」に感謝し帰路に着いたが、公園管理者は環境保全に努めていると声高に叫んだりしていない。
2024年05月30日
面白い習性をもったクモを見つけた

郊外の住宅地にある自宅の庭には、時々珍しい生き物がひょいと顔を見せる。平たい殻の周りに毛が生えたような準絶滅危惧種のケマイマイや、派手な豹柄をした絶滅危惧I類のツマグロヒョウモンなど。最近では同Ⅱ類のニホンアナグマが、丸い体に短い足で家の前の道をノコノコノコと歩いていた。
先日、妻が「足の先に白い毛が生えたクモがいた」と言いながら、スマホで写したばかりの画像を私に見せた。また絶滅危惧関係の虫かと思ったが、画面を拡大すると、足先の白いものはクモの網についた模様だった。
調べてみると、レース編みのような部分は「隠れ帯」と呼ばれている。隠れ帯のデザインは、クモの種類によって違いがある。このクモは足先からX字状に四方に伸びており、コガネグモの特徴らしい。隠れ帯は単なる飾り物ではなく、餌の捕獲効率を高める秘密兵器であることが、近年の研究で分かってきたという。
コガネグモは、鹿児島では姶良市の伝統行事「加治木町くも合戦大会」で競わせるクモとしてよく知られている。6月第3日曜日に開かれ、毎年テレビニュースで、長さ60㌢の棒上での一騎打ちの熱戦が報じられる。しかしコガネグモが、隠れ帯を作るなどの生態はほとんど伝えられない。レッドリストではなかったが、「ばあばのスクープ写真」として生き物好きの孫に送った。
岸田首相は支持率アップを願って、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」のカンダタのように、訪米という細いクモの糸を手繰っていった。が、衆院補選の全敗で、その糸もカンダタ同様プッツリと切れてしまった。
2024年04月29日
「メダカの学校」の波紋は消えない

社会的活動をしてきた団体が、会員の高齢化で解散する話を、ニュースや私の周辺などで見聞きするようになった。
「メダカの学校」は、フルート奏者の池田博幸さんが「甲突川にメダカを呼び戻そう」との思いで作った、鹿児島の環境保護団体だ。発足した三十数年前、小川を泳ぐメダカを観察しながらの講演会に足を運んだ。自然のメダカが減っていることを入り口に、広い視野での環境問題の話だった。その場で、池田さんに私たちの団体での講演を依頼。しかも話の間にフルートのミニコンサートまでお願いした。
会当日の1週間ほど前に「会場にピアノはありますよね」と池田さんからの電話。音楽に無知の私は、フルート演奏にピアノ伴奏が必要など知らなかった。電話口では「当日は準備できています」と答えたものの、会場は旅館の大広間、ピアノなどない。中止もやむなしが頭をよぎった。
大学時代の知人が楽器店に務めていることを思い出し、店まで走った。「そんな無茶な話を」と、彼は困惑顔で手を横に振るだけ。何度も頭を下げなんとかグランドピアノを借りられた。一難去ってまた一難。旅館の廊下や階段は狭くピアノは運べない。ピアノを乗せたトラックが、大広間の外に駐車できると分かり、窓を数枚はずしピアノを室内に入れた。
「メダカの学校」は一時は400人の会員がいたが、NPO法人はすでに解散。年1回の「メダカのコンサート」も、運営者の高齢化でこのほどFINALを迎えた。しかし「学校」に集った若い「メダカ」たちは、別の「川」や「池」で波紋を広げて泳いでいる。
2024年03月28日
祖母の まじないの様な入浴作法

寒い日が続くと、冷え切った体を温めてくれる入浴が楽しみだ。湯に肩までつかっていると、白い湯けむりの中で思い浮かべることがある。
子どもの頃住んでいた社宅は、戦後すぐに建てられ内風呂がなかった。歩いて10分ほどの会社の共同浴場に通うことに。ボイラーの燃料には会社の製品のコークスが使われていた。
社名が焼き印され、家族の氏名が墨書きされた木札が「通行手形」。番台に見せて入った。親戚が泊まりに来た時は、隣近所からこの木札を借りた。番台のおじさんは「いちげんの客」と分かっても、安宅の関の富樫氏のように黙認してくれた。
脱衣所では、壁に貼られた近所の映画館のポスターなどを眺めながら、脱いだ服を籐のかごにいれていた。浴場入口のガラス戸は湯気で曇り、小さい子らの落書きのキャンバスだった。浴槽は結構広く大人15人くらいがゆっくり入れた。空いている時は泳ぐ子もいたほどだった。共同浴場は子どもにとって、仲間との遊び場でもあった。
小学校低学年まで母や祖母と一緒に女湯に入ることも。祖母は「肩までつからんと湯冷めする」「風呂から上がる前にあと20数えるんよ」と口うるさかった。お湯から上がる前も「体が芯からぬくもる」からと、両手に溜(た)めた冷水を私に飲ませ、再度湯船につかるように言った。祖母が入浴時に毎回していた、まじないのような冷水の作法。効き目があったのか、なんとなくポカポカ温まったような気がしていた。
さて「裏金の湯」に浸っていた自民党議員。国民は落選という冷水を浴びせるしかないだろう。
2024年02月28日
能登地震で29年前の震災当日を思う

元日は、前の晩から泊まっていた孫と娘夫婦で過ごした。昼前から食卓を囲んだ。小、中、大の三種の杯で飲むお屠蘇(とそ)からスタート。孫には「真似だけ。少しなめるぐらいはいいか」と言いながら、年少者から順に杯を回していった。穏やかな昼下がり、お節やアルコール類などを口にしながら世間話に花を咲かせていた。しかし夕方、見ていたテレビが地震速報の特番に切り替わると、お屠蘇気分は吹き飛んだ。
能登半島地震はそれから連日、被災や支援状況が報道されている。ニュースを見ながら29年前の阪神・淡路大震災発生の1995年1月17日を思い出した。
その日は、2人の娘の学校が振替休日で、妻ら3人は朝寝坊を決め込んでいた。彼女らが起きないようにテレビも付けず静かに朝食をすませた。大阪の印刷所に出張するためバスで空港に。空港のテレビで初めて関西地方の地震を知った。しかし、搭乗した大阪(伊丹)行きの飛行機は、何のアナウンスもなく定刻どおり離陸した。テレビ映像の火災は局所的なのかと思った。今なら、乗客の安全を第一に考え欠航になっていただろう。
大阪空港は水道管に亀裂が入ったのか、水が壁面を流れ落ち通路が水浸しに。当時はスマホどころか携帯電話も普及しておらず、とにかく印刷所まで行こうと決心した。私鉄電車や高速バスはすべて運休。路面バスだけが走っていた。空港職員にバス停の場所を聞いて1㌔ほど歩いた。周りを見ながら進むと、古い民家の屋根や土壁が壊れ落ちていた。徐々に地震の激しさを実感したが、都市が壊滅していたとはまだ知らなかった。
2023年12月27日
ドードー巡りになる 復活か保護か

半世紀前の1970代初頭、日本はアリスブームだった。今年没後40年の寺山修司をはじめ著述家から、宇野亜喜良、金子國義ら画家まで「不思議の国のアリス」をテーマにした作品を次々に発表した。ディズニーアニメまでも再上映された。
そのブームは私の本棚にも。原作を読んだことがなかったので角川の文庫本を買った。夢の中の話しという「落ち」は知っていたが、突拍子もないキャラクターが奇事怪事を起こすのが楽しく読み進んだ。しかし、いくつも出てくる洒落や言葉遊びの文章に手こずった。初版の19世紀の英国人ならすんなり読めたのだろうが、翻訳した岩崎民平の「注」を見てもぴんとこない個所が多かった。岩崎自身も「解説」で「(洒落の)訳がめんどうで、はなはだ不手際なものがある」と書くほど。
こんなことを思い出したのは、新聞に「アリス」の作中に出てくるドードーのことが載っていたから。全国紙に「絶滅したドードーを米バイオ企業が復活を狙っている」との科学記事。
ドードーはインド洋のモーリシャス島にいた空を飛べない大きな鳥。「不思議の国」のジョン・テニエルの挿絵でも有名だ。16世紀末から同島に上陸したオランダ探検隊などの食料にされ、17世紀に絶滅した。
バイオ企業は現代の近縁動物を利用して、映画「ジュラシック・パーク」のように現代版ドードーを「復活」させるらしい。一方で「復活より、絶滅を防ぐための環境保護に力を入れるべき」との批判も。この対立はドードー巡りになるが、生物を絶滅、絶滅危惧にしたのは人間の営みによることはほぼ間違いない。
2023年08月25日
日本人が 日本に密航した時代が

NHK総合でドラマ「やさしい猫」が6月下旬から放映された。直木賞作家の中島京子さんの同名小説が原作。主人公のシングルマザーと娘が、スリランカ人の男性と家族になったことで、国を相手どった裁判に挑んでいく話だ。
ドラマの第3話から、家族の裁判を支える恵耕一郎弁護士が登場した。名バイプレイヤーとして知られる滝藤賢一さんが演じていた。恵弁護士にはモデルがいる。入管問題、外国人技能実習生問題に長年取り組んでいる指宿昭一弁護士だ。
私が原作本を読んだきっかけは、奄美群島内の役場職員がSNSに投稿した「知人の奄美2世の指宿弁護士をモデルにした登場人物が描かれる小説が出版された」を見たから。奄美では、県外に出て暮らす人を1世、その子、孫を2世、3世と呼ぶ。独自の歴史や文化を持っていることに由来すると思われる。
その一つが戦後、北緯30度付近に国境線が引かれ、沖縄とともに米軍統治下に置かれたこと。暮らしのため日本本土への「密航」もあった。大相撲の3代目朝潮も、奄美の徳之島から密航した。こうした歴史から、本土への転居を「移民」と感じたのだろうか。
今年は奄美の国境が消えてから70年。7月末に奄美から330㌔離れた鹿児島市まで、7日間かけてカヌーで渡った若者らがいた。日本復帰を訴えた「密航陳情団」の航路をたどった。メンバーは「命がけの苦難を実感した」と語っていた。
今の在留外国人の暮らしにくさと、かつて日本人が日本に密航しなければならなかった、国境とはなにかも教えてくれた「やさしい猫」だった。
2023年03月02日
駐輪中のヘルメットは どこに置こう

全ての自転車利用者に4月1日からヘルメットの着用が義務づけられる。罰則のない努力義務ではあるが。13歳未満は、保護者に着用努力義務がすでに課せられている。義務化について警察庁は、自転車関連の死亡事故の約6割が頭部のダメージによること、ヘルメットなしの人の致死率は、被っていた人の約2.2倍高くなっていることなどをあげている。
妻は10年ほど前から電動アシスト自転車に乗っている。坂道の多い団地内のスーパー、コンビニの買い物に重宝している。義務化に不満顔だ。交通量の少ない団地では、ヘルメットを被った時の違和感や、視野が狭くなる方が問題と考えている。それ以上に駐輪中のヘルメットの置き場。自転車に掛けていると、盗難とかいたずらが気にかかる。といって持って店内に入ると、手荷物が増えてストレスになる。
今ではバイクやオートバイの運転にヘルメット着用は当たり前。60年ほど前は、日本でも大人たちはノーヘルで乗っていた。死亡事故も多発し「ヘルメットを被ろう」キャンペーンが始まったことを覚えている。
ローカルテレビのニュースでも取り上げられ、当時オートバイ通勤していた父親が、街頭インタビューをされた。放送前日にリハーサルが。耳当て付きのヘルメットでは、記者の声が聞きにくいと父は告げたが「ヘルメット姿を映したいので」と押し切られた。生放送のニュースは、当時は珍しかったヘルメット姿の男性を、記者が偶然見つけた感じで始まった。
今回は、ヘルメット姿で自転車に乗る高齢者へのインタビューが、毎日のように流されるかな。
2022年06月27日
大学構内で アオサギに出会った日

5月4日がみどりの日という訳ではないが、ミニ森林浴をしようと鹿児島大学の植物園に出掛けた。この植物園の歴史は古く、同大農学部の前身である鹿児島高等農林学校が開校した1909年に設置された。約1㌶ある園には、南九州から南西諸島の約250種の樹木が植えられている。絶滅が危惧されるハナガガシや固有種のケラマツツジなどの希少種もある。農学部の実習場だが、一般開放されているため市民の憩いの場にも。
玉利(たまり)池の縁を通って植物園に向かった。私の学生時代は、この池の周りは大学祭の神輿(みこし)づくりの場所に使われるくらいだった。池の水も濁りきっており、水溜(た)まりの「溜まり」池と思うほどだった。十数年前から水抜き清掃をし、池を囲むようにベンチが置かれ、学生や教職員の親水性のくつろぎの場に変わっている。
池を巡りながら、池に突き出た築山に鳥の置物が見えた。「これはいらないな」と思いながら見るとゆっくり動いている。本物の鳥だった。細長い首にグレーの胴体。90㌢くらいの体長なので小さなツル?頭部に長さ10㌢ほどの黒い冠羽が見えた。アオサギだった。
飛ぶところを見たいなと思ったが、一動作をすると1分ぐらいそのまま。大声で通り過ぎる学生がいたが、まったく臆することなくじっとしていた。池にはウナギもいるので、その獲物をずっと待っていたのかもしれない。
アオサギは甲突川では時々見かけるが、キャンパスの一角で遭遇するとは。自然のままの隣の植物園と池の再生で住みやすい環境になったのかもしれない。ミニバードウオッチングも楽しめたみどりの日だった。
2022年06月01日
暮らしの中にあった 戦争の傷跡

小高い丘の上に建つ高校に通っていた。坂道に続く80段程の石段の先に校舎が。校名が書かれた校門が、石段途中の踊り場に建っている。入学式の日「校門に門扉がないことに気づきましたか」の問いかけで、校長あいさつが始まった。鉄の扉は戦時徴用で拠出され、その残像が生徒を迎え入れていた。
幼い頃、防空壕(ごう)に住んでいる人がいたし、遊び場の野原を掘ると小銃弾が出てきた。祖父は冬が近づくとカーキ色の国民服を愛用し、和だんすの奥にゲートルをしまっていた。祭りの日には、白装束の傷痍(しょうい)軍人の楽曲が会場に流れていた。
戦後生まれであるが、暮らしの中に、戦争の傷跡がかさぶたのように残っているのが見えた。祖母と母は戦時中の一番の犠牲者は、国の中枢にいた人ではなく国民、庶民だったことを繰り返し話した。傷は消えても、伝えるべき記憶は消してはいけないと思った。
ロシアのウクライナへの軍事侵攻が毎日報道されている。すさまじいミサイル攻撃が住宅、学校、医療施設、避難場所を破壊し、居住地周辺で戦闘が交錯している。必死に戦火を逃れる姿や、泣き叫ぶ女性と子どもたち。家族を失った人たちの悲嘆。瓦礫(がれき)になっていく街。
「東側」であれ「西側」であれ、生活の場を戦場にすれば、その悲惨さは同じである。かつては自民党の政治家にも、自らの体験から野党以上に戦争反対の姿勢を崩さない議員がいた。しかし「ウラジミールと同じ夢を見てい」た男は、戦闘参加を煽(あお)るように「敵地中枢攻撃、核共有、防衛費のGDP2%以上」と叫ぶ。安倍の悪夢の道連れになりたくない。
2022年05月06日
アオサギ
5月4日がみどりの日という訳ではないが、鹿児島大学の植物園にミニ森林浴に。
玉利池の縁を通って植物園に向かった。学生時代は、この池の周りは大学祭の神輿づくりの場所として使われるくらいだった。池の水も濁りきっており、水溜まりの「溜まり」池と思っていた。十数年前から水抜きの清掃や、池を囲むようにベンチも置かれ学生や教職員の親水性の憩いの場になってるようだ。
池をめぐりながら、池の中に突き出た築山のような場所に鳥の置物が見えた。「これはいらないな」と思いながら見るとゆっくり動いている。本物の鳥だった。細長い首にグレーの胴体。90cmくらいなので小さなツル?頭部に長さ10cmほどの黒い冠羽が見えたのでアオサギ。飛ぶところを見たいなと思ったが、一動作をすると1分ぐらいそのまま。大声で通り過ぎる学生がいたが、まったく臆することなくじっとしていた。玉利池にはウナギもいるということなので、その獲物をずっと待っていたのかもしれない。
アオサギは甲突川でも時々見かけるが、キャンバスの一角で遭遇するとは。ミニバードウオッチングも楽しめた。




玉利池の縁を通って植物園に向かった。学生時代は、この池の周りは大学祭の神輿づくりの場所として使われるくらいだった。池の水も濁りきっており、水溜まりの「溜まり」池と思っていた。十数年前から水抜きの清掃や、池を囲むようにベンチも置かれ学生や教職員の親水性の憩いの場になってるようだ。
池をめぐりながら、池の中に突き出た築山のような場所に鳥の置物が見えた。「これはいらないな」と思いながら見るとゆっくり動いている。本物の鳥だった。細長い首にグレーの胴体。90cmくらいなので小さなツル?頭部に長さ10cmほどの黒い冠羽が見えたのでアオサギ。飛ぶところを見たいなと思ったが、一動作をすると1分ぐらいそのまま。大声で通り過ぎる学生がいたが、まったく臆することなくじっとしていた。玉利池にはウナギもいるということなので、その獲物をずっと待っていたのかもしれない。
アオサギは甲突川でも時々見かけるが、キャンバスの一角で遭遇するとは。ミニバードウオッチングも楽しめた。
2022年04月03日
酢工場の臭いがする 図書館の一角

明治後期と戦後すぐの鹿児島県内の出来事を知りたくて、県立図書館を訪ねた。当時の新聞記事を見るため、閲覧願いを出した。館内には1882年2月から2年前までの地元新聞が、マイクロフィルム化されている。
マイクロフィルムは、カメラで新聞などを縮小撮影し、マイクロリーダーという投影機で拡大し閲覧する。一般の写真フィルムより画像粒子が細かく、新聞の小さな文字も記録できる。10億4000万画素に相当する。同館は1973年5月にこの事業をスタートした。
10件ほど依頼したが「フィルム劣化のため閲覧不可能な紙面があります」と伝えられた。今のマイクロフィルムは100~300年の耐久性があり、改竄(ざん)が困難なため重要情報の保存に適している。ただし、1990年代初期までの製品は30年程度で劣化する。同館では「早いものは18年目から始まった」。フイルム素材が加水分解され表面に酢酸ができる「ビネガー(西洋酢)シンドローム」が起きるためだ。保管場所のドアを開けると、ツーンと酸っぱい臭いがする。全国で同じ問題を抱えているだろう。
新聞という記録財産の価値は、紙面から時代の空気が感じられること。記事、写真、広告などからその日が伝わってくる。1949年4月の事を調べたが、紙面は表裏の二面だけ。戦後の物資不足で、印刷用紙が統制割り当てだったことも知った。
同館では、劣化したフィルムは再作成かデジタル化を検討しているが「予算の関係で具体化は進んでいない」と、職員はもどかしそうだった。県民の貴重な記録財産が再生できなければ、それは県政の劣化だろう。